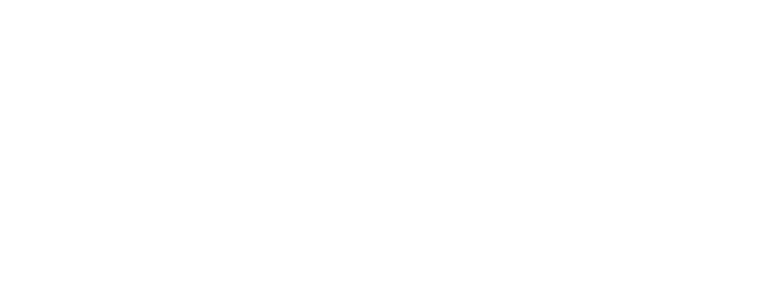



-
- フリーワード検索



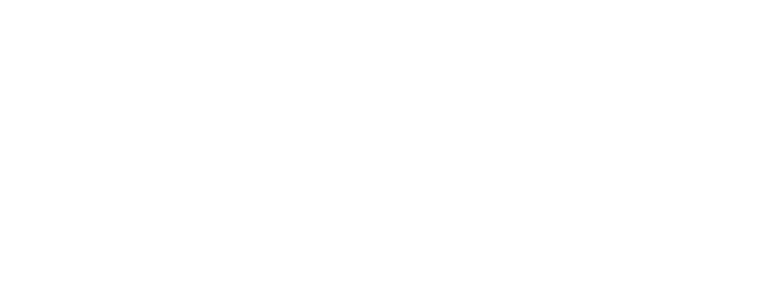
プロフェッショナルユースに対応し,CAD,グラフィックスデザインをはじめ,高度な技術計算や事務処理などに幅広く普及した業務用の高性能なコンピュータ「ワークステーション」。多数のユーザー要件を満たすために,長時間の連続使用や高い拡張性,高速処理を実現する高性能CPUの実装など,厳しい使用環境に対応した高い“安定性”と“信頼性”が,以前にも増して要求されています。
かつてはUNIXベースで高価格であったため,一般ユーザーには手の届かないマシンでしたが,近年はWindowsベースの「PCワークステーション」の普及により,企業のオフィスから店舗,SOHOにいたるまで,数多くのユーザーにとって身近なものとなっています。
コンピュータシステム,周辺機器,ソフトウェア製品の開発・製造などを手掛ける, IT機器製造および情報サービス業のJ社。新たなPCワークステーションの開発に着手していた同社では,大量のデータ処理や演算負荷の高いアプリケーション利用など,市場ニーズに対応するために,次期モデルへ新たな高性能CPUの採用を決定していました。
しかし,高密度実装された機器内部において,発熱は処理速度の低下や機器の不具合,さらに故障を引き起こす原因ともなりかねません。CPU本来のパフォーマンスを発揮し,機器の“安定性”と“信頼性”を向上するためにも,“高い冷却性能”は必要不可欠でした。
同社では,現行モデル開発時に冷却性能の見直しをおこなっており,「40mm角28mm厚」タイプのファンを2台搭載していました。この仕様であれば,次期モデルにおいても求められる冷却性能を十分に満たすはずでした。しかし,冷却ファンの仕様について大幅な見直しを迫られることになります。
現行モデルにおいては,ユーザーからしばしば,「騒音が大きく,業務に支障をきたす」との指摘を受けており,さらに設置する場所によっては,共振によって振動音が増幅されてしまう事例もありました。
このためJ社では,“低騒音化”と“低振動化”を,次期モデル開発における課題と捉えていました。問題は,いかに高い冷却性能を保ちつつ,これらの要件を実現するかという点です。同社開発部のD部長はこう語ります。
「PCワークステーションが,利用者にとって身近なものとなり,専用のサーバルームではなく,事務所内に設置されることが多くなってきました。そのため,高性能化はもちろんのこと,ユーザーにとって耳障りとならない“静音化”が非常に重要な要素となっています。競合との競争に勝つためにも,次期モデルの低騒音化の実現は必須でした。」
現行ファンで課題をクリアするためには,大幅な構成パーツのレイアウト変更や,共振による騒音を低減するため装置剛性の向上が必要であると判断しますが,開発スケジュールを考えるとそれもままならず,D氏らは大きな壁に直面してしまいました。
※ファンの騒音について詳しくは山洋教室ファンの基礎知識:ファンの騒音と音圧レベル
数日後に同社を訪れた山洋電気の営業担当は,D氏らより詳細なヒアリングをおこない,低騒音化に向けたポイントを整理しました。
「同サイズ(40mm角28mm厚)で,冷却性能を低下させずに,低騒音化を実現するには,ファンを構成するすべての部品を見直し,新しいファンを開発する必要がありました。しかし,J社の開発スケジュールの変更はできないため,ファンのサイズ変更を提案しました。」(山洋電気 営業担当)
J社は,既存の「40mm角28mm厚」タイプのDCファン2台構成に対して「60mm角25mm厚」タイプのDCファン1台構成の提案を受けます。試行錯誤を繰り返すなかで,次期ワークステーション内の各パーツの配置を見直し,60mm角までならば搭載できることがわかりました。
さっそく,山洋電気は60mm角DCファンの評価用サンプルをJ社に納品。同社はファンの評価を始めます。
試作機での実機検証をおこない,ファンが期待通りの効果を発揮することを確認。1台でも十分な冷却性能を得られることで,低騒音・低振動化に対する課題をクリアすることに成功しました。
「想像以上にファンの特性が良く,騒音や振動の面でも問題なく,期待通りの効果を発揮しました。そのため,開発スケジュールが短縮できました。これらに加え,スイッチングノイズも大幅に低減されていました。現行のファンでは,低速回転時に「ジリジリ」という磁気騒音が発生していましたが,ソフトスイッチングをするICが搭載されており問題ありませんでした。」(D氏)
ファンを実装することで,現行ファン2台で0.48m3/minであった風量を,1台で0.58m3/minを実現することができました。かつ,騒音は33db (A)から24db (A)への低減を実現しました。また,ファンの風きり音だけでなく,筐体との共振により発生する振動音も低減することができました。今回の「DCファン」導入について,D氏はこう総括しています。
「24dBといえば,衣擦れの音より小さいレベルです。あまりの静かさに驚きました。これまでのファンに比べて,30%の低騒音化を達成できました。しかも,1台にしたにも関わらず,風量は0.10mm3/minアップしています。また,2台構成から1台構成になったことで,コスト低減も図ることができました。」
ユーザーのニーズを満たしながらも,パフォーマンス向上に成功した同社の製品は,市場優位性を確立し,今後さらなるシェア拡大が期待されています。
公開日: