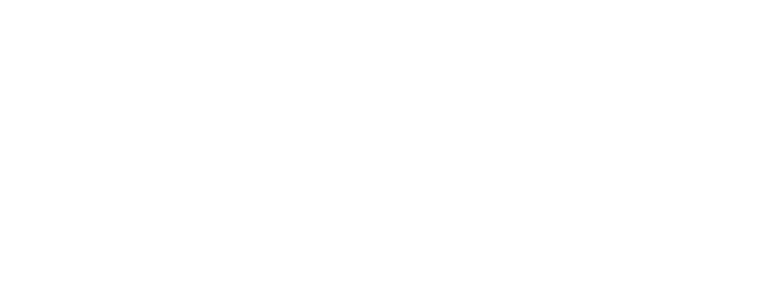



-
- フリーワード検索



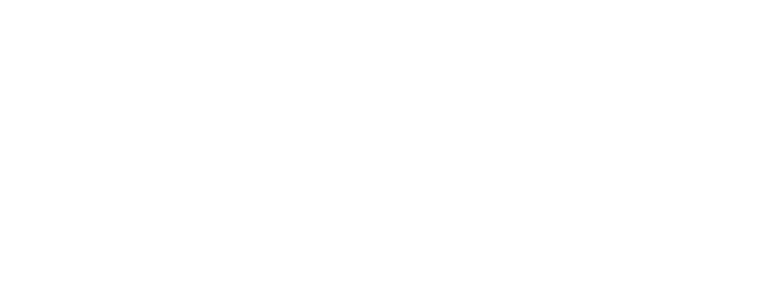
1895年に発見されたX線は,身体内部の観察を可能とすることで近代医学の驚異的な発展に寄与し,その後100年以上にわたり「確定診断」の手段として用いられてきました。近年,フィルムを用いないX線撮影技術が確立したことで,3D診断やX線透視下でおこなう治療など,X線診断システムに求められる機能は多様化しています。
しかし,医療機器には性能以外にもクリアしなければならない課題がたくさんあり,開発者を悩ませているのです。
医療機器の企画・製造・販売を手掛けるU社は,高度化する医療ニーズに対応するため,新たなX線診断システムの研究・開発を進めていました。
この次世代型のX線診断システムは,X線透視下における外科的処置や,頭部から下肢までの全身撮影などを可能とするもので,処置技術者の意思通りのポジショニングと安定した鮮明な画像を得るため,アームや診療台にはスムーズかつ高精度な動作が求められます。
しかし,これらの実現は一筋縄ではいかず,U社の開発部門を悩ませていました。同社では各製品に同じモデルのサーボシステムを汎用的に使用していましたが,新モデルの試作機に実装して検証したところ,三次元測定データを作成する際に,アーム先端部の振動を十分に抑制することができなかったのです。同社技術開発部のJ氏はこう語ります。
「サーボシステムは10年来使用し続けてきたタイプのため,まだアーム先端部の振動を抑える機能を持っていなかったのです。実は,薬事法の関係で,搭載する部品に変更が加わるとその都度申請・承認フローを通さなければなりません。申請には長い時間を要するので,開発期間やコストを考えると,承認済みの部品を流用することが望ましかったのです。しかし,処置効率を上げるというユーザーのニーズを満たすためには,思い切って新しいサーボシステムを選択するほかありませんでした。」
加えて,J氏を悩ませていたのが,装置の小型化の問題でした。
処置室内の限られたスペースにおいて,複数の医療機器を使用し高度な医療処置をおこなう必要があります。そのため,各医療機器の省スペース化は必須でした。
また,従来のX線診断システムでは,装置全体に6軸のサーボモータが搭載されていましたが,その仕様ごとに2メーカーの製品が混在していました。今まではそれでも問題はなかったのですが,次期モデルでは,コントローラとサーボシステムをシリアル通信で結ぶことを考えていたので,メーカーによって通信仕様が異なると,システムが複雑になってしまいます。
「シリアル通信にして省配線化すると,コスト削減だけでなく,トラブルの低減やメンテナンス面でも大きなメリットがあります。」(J氏)
詳細な説明を受けた後,J氏は評価用の試作サーボシステムを手配して評価をおこないました。アーム部分のスムーズな動作と高精度な画像の要となる,「新たな制振制御」の性能を検証したのです。
「制振制御機能を初めて使いましたが,予想以上でしたね。以前のシステムでは,どうしても移動時にアーム先端部の振動が大きくなってしまうことがあったのですが,振幅を1/10以下にまで抑えることができました。どのような動きをさせても,アーム先端の振動は肉眼では分からないほどでした。振動を抑制できれば,当然ながら画像精度がアップします。処置効率向上に大きく貢献すると確信しました。」(J氏)
また,アンプの検証では,オープンシリアル通信規格「EtherCAT」に対応していることで,他社製コントローラでも問題なく動作することを確認しました。
「コントローラ側の開発には時間がかかりそうですが,転送レート100Mbpsの超高速フィールドバスシステムというだけあって,これまでとは桁違いの高速転送・高速処理で,正確な同期性の確保が期待できました。また,他社製サーボシステムを含む複数の機器も同じEtherCAT通信で接続できます。10年来のサーボアンプを置き換えることで体積比が62%も小型化されますし,さらにモータの全長も短くなったので,装置全体で大幅な省スペース化が図れると期待が持てましたね。」(J氏)
新しいサーボシステムの採用は,小型化はもちろん,配線工数の削減や開発コストの削減,不具合・ミスの低減など,さまざまな可能性を秘めています。これらは,同社の開発課題を解決するうえで大きな一歩となりました。
こうして十分な検証を経た末に,新たなX線診断システムの開発に有効と判断したU社は山洋電気の新型ACサーボシステムの採用を決定。
その後,同社はコントローラの開発と並行して,試作コントローラを組み付けて動作検証を実施。その際に山洋電気はサービススタッフを派遣して最適なゲイン調整をフォローし,その後もU社へのサポートを継続していきました。
「常に現場に直接赴いていただいたので,最適な特性を出すためのゲイン調整をおこなうことができましたし,その後のこまごまとした不明点にもスピーディに回答を得られ,設計開発をスムーズに進めることができました。サーボシステム自体の高性能さに加えて,こうしたサービス力があったからこそ,次期モデル開発に成功できたと感じています」(J氏)
まだ試作機段階ですが,次期X線診断システムは期待通りの性能を発揮。山洋電気製サーボシステムは同社の新たなX線診断機において,装置サイズを15%削減,画像精度を約20%向上という効果をもたらしました。
J氏はこう語っています。
「山洋電気の提案によって,新たなX線診断システム開発に活路が見出せました。医療技術の進歩やニーズの多様化から,より高度な技術を搭載した装置開発が至上命題となるなかで,すぐれた機能と性能をもつこのサーボシステムは,これからも大きな力になってくれると思います。」
公開日: