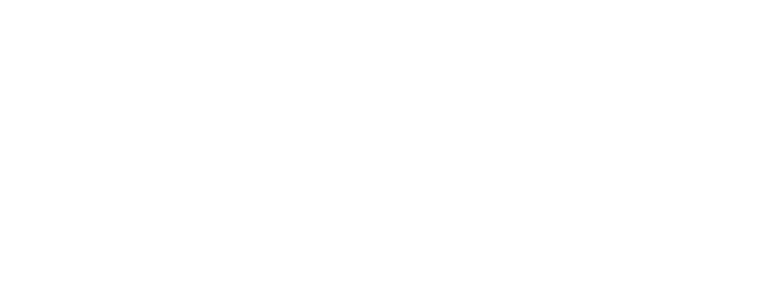



-
- フリーワード検索



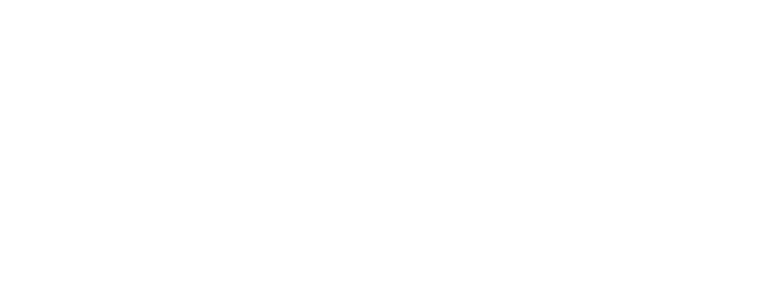
F社では生化学自動分析装置の新モデルの開発に取り組んでいました。しかし,検査のサイクルタイム向上を目指して試行錯誤するも,次々と問題に直面しました。
製品開発部のT氏は次のように語ります。
「新モデルでは検査速度を向上させるために,機構を軽量化し,モータ速度をアップさせることでサイクルタイムの短縮を図ろうとしました。しかし,試薬滴下機構がときどき位置ズレするという現象が確認されました。位置ズレの原因を探ったところ,ステッピングモータに脱調が発生していることが分かりました。」
T氏は,脱調の原因がトルク不足ではないかと考えました。そこで,脱調対策として,ドライバの駆動電流を上げてトルク不足を補うことにしました。
「駆動電流を上げると,脱調の問題は解決しましたが,想定していた以上にモータが発熱し,周囲温度が上がってしまいました。発熱は検体に悪影響を及ぼす可能性が高く,検査装置としては致命的でした。」(T氏)
T氏は発熱を許容範囲に抑えるために,試作と検証を繰り返しました。しかし,なかなか良い結果が得られず,時間ばかりが過ぎていきました。
装置の制御部の冷却には,山洋電気のファンを使用していました。そこで,T氏は,熱対策のアドバイスをもらうために,山洋電気に相談することにしました。装置の要件を詳しく確認していくなかで,担当者からは,モータの置き換えを提案されたのです。
「モータの発熱を抑えるために,クローズドループステッピングシステムが有効との提案を受けました。クローズドループステッピングシステムは,ステッピングシステムと異なり,サーボシステムのようなフィードバックループが組まれています。
そのため,負荷に応じて必要なトルクを制御し,必要な分だけ電流を流すようになっており,発熱も最低限に抑えられるということでした。また,位置ズレの原因となる脱調の心配もないので,経年変化による負荷変動にも強くなり,装置としての安定性が期待できます。」(T氏)
山洋電気の担当者からさらに詳しい説明を受け, T氏はさっそく試作機で評価をおこないました。
「もともとパルス列入力タイプのドライバを使っていたので,上位装置と接続するための駆動プロファイルを変更することなく,現行のステッピングドライバから簡単に置き換えることができました。そして,目標としていたサイクルタイムの短縮に成功したのです。
山洋電気の提案のおかげで,予定どおりに新モデルを製品化することができました。さらに,クローズドループステッピングシステムは,低振動なので騒音が抑えられるというメリットも得られました。」(T氏)
F社ではこれまでの装置には主に,ステッピングモータを採用していました。
「今回の開発を通して,クローズドループステッピングシステムのさまざまなメリットが分かったので,今後は他の装置にも水平展開したいです。」とT氏は語っています。
ステッピングモータについて詳しくは「ステッピングモータとは? 仕組み,種類,使い方(駆動方式・制御方法),メリットや特徴を解説」もご覧ください。
公開日: